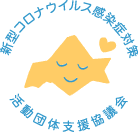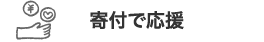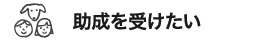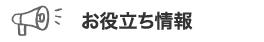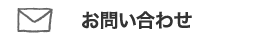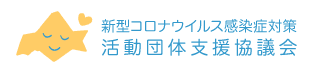団体からのお知らせ・インタビュー
[インタビュー]トラブルの受付と講座の開講は事業の両輪~消費者支援ネット北海道 大嶋さん・小森さん
![[インタビュー]トラブルの受付と講座の開講は事業の両輪~消費者支援ネット北海道 大嶋さん・小森さん](http://cdn.goope.jp/164450/231018115104-652f48184d13b.jpg)
NPO法人消費者支援ネット北海道
成年年齢引き下げに伴う若年者向けの消費者被害防止のための事業
(令和5年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 まちづくりの推進分野)
消費者支援ネット北海道は、不当な勧誘や不当な契約で被害を受けた消費者に代わり、差止請求訴訟を行なうことができる適格消費者団体として2010年に認定を受け、活動を行ってきました。並行して、消費者のための教育・啓発活動にも取り組んでおり、教材の作成やセミナーの実施、地域における消費生活協力員養成講座などを開催してきました。
今回は、理事で消費生活アドバイザーでもある大嶋明子(おおしまあきこ)さんと小森公一(こもりこういち)さんにお話を伺いました。
※右写真:インタビュー時の様子。左から大嶋さん、小森さん
 全国に4団体しかない特定適格消費者団体のひとつ
全国に4団体しかない特定適格消費者団体のひとつ
― まず、どのような活動をされている団体なのかを教えてください
2007年に国が一定の要件を備えた消費者団体に対して、消費者に代わって訴訟を起こせるという「消費者団体訴訟制度」が導入されたのを機に、差し止め請求などができる権限を持った「適格消費者団体」というものができました。そこで、この適格消費者団体になることを目指して、北海道生活協同組合連合会(北海道生協連)・北海道消費者協会が幹事団体となって、法曹界などの各方面に呼びかけて作った団体が、私たち消費者支援ネット北海道(ホクネット)です。これまでに、事業者に対して法に基づく申し入れを延べ200件近く(事業者数で約180社)に行ってきました。
2016年に消費者裁判手続特例法が施行され、「特定適格消費者団体」による被害回復の訴訟が可能となりました。消費者裁判手続特例法に基づき消費者が受けた被害について、訴訟と裁判手続きを行うことで、直接的に消費者の被害回復ができます。私たちは、2021年にこの特定適格消費者団体を全国で4番目※に付与されましたが、これはとてもハードルが高く、認定までの道のりがかなり大変でした。
※2023年10月現在、東京都・大阪府・埼玉県の消費者団体1団体ずつが取得しています。
― 弁護士や法律学者などの専門家はどのように協力されているのでしょうか
適格消費者団体に認定されるには、消費者が受けた被害を消費者から通報を受けて消費者関連法に基づいた検討をする部門を設けなくてはいけません。そのためには、理事などの役員として団体に在籍している者以外にも、法律家、弁護士、司法書士、法学の先生と、現場の情報として消費生活相談員による検討部門を作り、申入書を作成するとういう流れになっていますので、常に専門家と協力しながら活動を続ける必要があります。
― 通報の状況はいかがですか?
これまでもずっと通報を受け付けているのですが、ちょうど「特定」の認定を受けた前年に、通報が3倍に増えたことがありました。消費者センターからの紹介の方が多いのですが、情報提供を受けて団体として動くというようなことを消費者センターがある程度説明してくれるので、通報してくれる消費者が少しずつ多くなってきました。相談機関としての看板もありますので、「こういう相談があるんですけど……」と言って来られる消費者もいます。その場合はお話を聞いた上で消費者センターをご案内することもあります。
 若年層に寄りそう支援を展開
若年層に寄りそう支援を展開
― 今回の助成事業についてお伺いします
「成年年齢引き下げに伴う若年者向けの消費者被害防止のための事業」になります。私たちも毎日のように消費者トラブルに関した通報を受けていますが、その中でも特に、若年者の副業や脱毛エステサロンなどによるトラブルでの通報というのが一定数あるので、専門家の担当者を置いて対応しようということで申請しました。
受け付けた通報をもとに、大学や専門学校などに対して、学生さんたちがこんなトラブルに遭っていないかといった情報をお互いに交換し合い、講座を開催しています。通報の受付だけだと受身的ですが、講座は先手を打つためのもので、通報で実態を聞きながら、これまでに2校で学生向けの講座を開催しました。トラブルの受付と講座の開講は事業の両輪となっています。
― この事業を行おうとした背景や理由をもう少し詳しく教えてください
特定適格消費者団体になってすぐに始めたのが、脱毛エステサロンの問題でした。消費者センターからの情報提供もあったのですが、脱毛エステサロンのトラブルは、事業者の経営が傾いていたにも関わらず、永久脱毛と謳い一括前払いで30~40万円という高額な金額を請求し、実際にはそのサービスを受けられなかったというものでした。
事業の譲渡先には消費者への債務を一切引き継ぎすることなく、消費者への対応はしないどころか営業実態もなく、破産せずに何もしていないという状況だったのです。言ってみれば、私たちではどうにもならない状況でした。ただ、未だに「どうしたらいいのか」と、若い方を中心に通報があるのですが、そうなってしまうともう解決できません。受身だけでは消費者トラブルは減らせない、啓発も同時にやらなければいけないと思いました。
若い方には少しでも良いので「こういう事例があった」ということを聞いていただければと思う気持ちが強くあります。
― 実際に講座を進めてみた感想や手応えをお伺いします
講座では、実際に投資詐欺やクレジットカード詐欺などの実例を交えてお話をしています。一般の方だと、聞きたくて来られるので一生懸命聞こうとしますが、学生向けだと身に覚えのある人は耳を傾けてくれるような感じがするものの、自分には関係ないと思ってる人は話を聞いてくれないといった部分で難しいなという感じはありました。ですが、最後の方では質問も出てくるなど、それなりに手応えがあったのかなと思っています。
 自分には関係ないとは思わないで。一緒に消費者被害を防ぎましょう
自分には関係ないとは思わないで。一緒に消費者被害を防ぎましょう
― 若い方を含めてメッセージをお願いします
トラブルは意外と身近にあります。自分には関係ないみたいに思っている人もいますが、今は関係なくてもいつトラブルに巻き込まれるかわかりません。要するに悪質業者はプロなので、話がうまいから誰でも騙されます。だから自分は関係ないと思わないで、しっかり学んでおいてほしいと思います。
― こちらの活動に関わりたいという人はどのような関わり方ができますか?
ボランティアはいつでも募集しています。一緒に法的検討を行う場では、専門家と専門家による非常に高度な議論に接することができますし、民法や特定商取引法などの身近な法律に基づいて解釈するという、滅多にない実践の機会です。特に弁護士になりたての方には勉強になると思います。裁判で争うには理論武装が必要です。委員会ではいろいろな方向の考え方をそれぞれが出し合うので、解釈の仕方はとても勉強になると思います。これから法律家を目指す学生さんなどは、ぜひ当団体へ来てください。いい勉強になりますし、ぜひ一緒に活動して消費者被害を防ぎましょう。

インタビューを振り返って
消費者支援ネット北海道さんは、全国的にも4つしかない特定適格消費者団体として、これから活動がますます増えていくと考えておられ、今回のさぽーとほっと基金の伴走支援では、ICTを活かした事務作業の効率化を目指しています。相談内容も時代に応じて急速に変化する中で、組織運営においても新しいやり方を模索する姿勢に感銘を受けました(高山)
インタビュアー
高山大祐(たかやまだいすけ)
北海道NPOファンド
※インタビューは、2023年8月22日消費者支援ネット北海道事務所にて行いました。

[インタビュー]子育てを喜楽に~相互支援団体かえりん 星野さん
![[インタビュー]子育てを喜楽に~相互支援団体かえりん 星野さん](http://cdn.goope.jp/164450/231014110557-6529f78507c19.jpg)
一般社団法人相互支援団体かえりん
おさがり交換会開催とコドモフリマ会場併設
(令和5年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 イオン環境基金助成)
「ワンオペ育児」という言葉が一般化するほど母親が一人で育児を担うことが多い現代の日本。相互支援団体かえりんでは、様々な子育ての問題を自分たちで解決するため、“相互支援”を定着させることを目指し、おさがり交換会を始めとする“子育てが喜楽になること”を企画・実施しています。
今回は、代表の星野恵(ほしのめぐみ)さんにお話を伺いました。
※右写真:コドモフリマの様子
 子育てを喜楽に 産後をHappyに
子育てを喜楽に 産後をHappyに
― まず、かえりんの活動について教えてください
かえりんは、産後にうつ病になってしまう女性へのアプローチとして、産後うつ未然防止を目的に掲げ、2016年に市民団体として立ち上げました。産後に家に引きこもりがちになってしまう女性たちに、自発的に家から一歩出てもらう活動ということで、おさがり交換会を開始してもう8年になります。
活動地域は札幌市内がメインですが、室蘭でも常時活動していますし、千歳、北広島、江別など、札幌以外での活動範囲も広がっています。
 幅広い年代の親の悩みを解決する仕組みづくりをしたい
幅広い年代の親の悩みを解決する仕組みづくりをしたい
― 今回の助成事業について教えてください
おさがり交換会「おさがりくるりん」を開催します。子どもが大きくなって着られなくなった洋服で、まだ着られる状態のものを持参していただいて、欲しいという方に提供するという活動です。妊婦さんから10歳ぐらいまでのお子さんを持つご家庭を対象としています。
それから、おさがり交換会と並行して、「コドモフリマ」という活動を始めました。家にあるおもちゃなどの不用品を持ってきてもらい、安いものだと10円から、高くても500円までで、子ども自身が出品・出店します。実際に売れるかどうかはやってみるまで分からなかったんですけど、ほぼ完売でした。現状では出店してくださる方がまだ少ないので、こういった活動をしていることを広く認知してもらい、参加者を増やしていくことが今後の課題ですね。
コドモフリマをおさがり交換会と並行して開催していくことで、より幅広い年代の親の悩みを解決する仕組みを作りたいと思っています。子どもが大きくなるにつれて、親の悩みや課題は大きく変化します。例えば、コドモフリマでは子どもの金融教育という課題を解決するための役割を担えると考えています。現在はマネースクールなどの金融教育のコンテンツが増えてきていますが、情報の精査が非常に難しくて課題解決が進まないのではということを感じていたので、コドモフリマの活動で、実際に自分で値段を考えて物を売買することを通じて、「お金ってなんだろう」と子どもが考える機会になれば良いなと思っています。それと、コロナ禍においてコミュニケーションの機会が少なくなった中で、日常生活では味わえないような交流の場を提供したいというのもあります。


おさがり交換会の様子。みなさん持ち帰り専用の袋に詰めます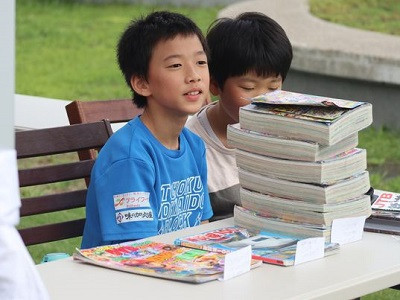
コドモフリマでは、子どもたち自身がお店番も。
 活動を拡げていきたい!
活動を拡げていきたい!
― 今後の活動についてお聞かせください
コドモフリマを開催する場所を拡大していきたいです。様々な地域の商業施設でお祭り的な感じで開催したいです。まずは全道が目標ですね!また、コドモフリマやおさがり交換会を継続的に実施できるように、組織基盤を構築したいと思っています。色々なステークホルダーと連携して、取り組みの輪を広げていきたいです。
― 今年度、当協議会メンバーによる伴走支援を行っています。伴走支援に期待することをお聞かせください
今回、ご協力いただける多くの人の想いを大切にしながら、それを活かしてビジョン・ミッションの実現に近づくために伴走支援を希望しました。ありがたいことに、かえりんの活動を応援してくれる人がたくさんいます。それをしっかりと受け止め、形にしていくための組織の仕組みを構築したいです。具体的には、個人・法人会員等の設定、企業や自治体と連携できる基盤づくりに挑戦したいと考えています。

インタビューを振り返って
産後うつ防止に向けて真摯に活動を継続してきたからこそ、かえりんには、たくさんの仲間や応援者がいます。その応援をしっかりと受け取り、活動を展開していくためにも、足腰の強い組織基盤を一緒につくっていきましょう!また、応援していただける人や組織の想いを活動に活かしていくためにも、より良い支援メニューを一緒に構築していければと思います。(久保)
インタビュアー
久保匠(くぼたくみ)
北海道NPOサポートセンター
※インタビューは、2023年8月29日にエルプラザにて行いました。
記事作成
森田涼雅(もりたりょうが)
北海道NPOサポートセンター夏季インターン
北海学園大学2年

[インタビュー]学生とシニアを繋ぎ、地域に「輪っこ」をつくる~wacco高木さん
![[インタビュー]学生とシニアを繋ぎ、地域に「輪っこ」をつくる~wacco高木さん](http://cdn.goope.jp/164450/231011133338-652625a238774.jpg)
学生団体wacco
北大周辺地域の繋がりを作る教室と生活支援サービス事業
(令和5年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 新型コロナウイルス感染症対策市民活動助成事業)
学生団体wacco(わっこ)は、年齢に関わらず、誰もが自分らしく生活できる世界を作ることを目標に、シニアが学生の若さと触れ、学生がシニアの経験を知ることで、学生とシニアの両方がWell Being(ウェルビーイング)になる状況を作るために、掃除や雪かき、外出付き添いなどのシニアの方々のお手伝いや老人ホームからの依頼による雪像づくりなどに取り組んでいます。
今回は、代表の高木翔成(たかぎしょうな)さんにお話を伺いました。
※右写真:高木さん
 若者が運営する高齢者のためのイベント
若者が運営する高齢者のためのイベント
― 今回の助成事業の内容や経緯について教えてください
月1~2回、高齢者向けのイベントを行うというものです。具体的には、VRゴーグルの体験会やスマホ教室、留学生との交流会など、この一年で15回程度の開催を予定しています。
VRゴーグル体験会は、宇宙ステーションやヨーロッパなどを見てもらい、とても喜んでいただけました。初めて体験したという方が多く、「見ているだけではつまらない」「ゲームがしたかった」という方もいらっしゃいましたが、概ね楽しんでくれたと思います。
これまでにVR体験会は1回、スマホ教室は2回行いました。7月にはインドネシアの留学生との交流を行い、留学生に作ってもらったクイズや、日本語と英語を混ぜてインドネシア語の練習もしました。
waccoの通常事業では、訪問型のお手伝い(生活支援)サービスを行っています。高齢者からの依頼に対して学生が、基本は1対1で対応しています。これまでに自宅から出ない高齢者の方にたくさん出会ってきたので、そういった方々が外出するきっかけを作れたらと思い、今回の事業を企画しました。
VRゴーグルを使えば宇宙まで行けるので、良いですよね!

スマホ教室の様子
 試行錯誤をいろいろしながら
試行錯誤をいろいろしながら
― 事業を実施して感じた課題や発見を教えてください
自宅から出ない高齢者にイベント会場に来てもらうということは、なかなか大変でした。付き添いが必要であったり、足の悪い方に来てもらうことはなかなか難しく、今後の課題でもあります。スマホ教室は1対1で行っているのですが、シニアと学生の数をぴったり合わせるというのも大変で、急に欠席される方や、申込みなく参加される方もいらっしゃるので、前日にwaccoメンバー以外からも学生を募集するなどして、数を合わせられるようにしています。
内容も、授業形式のスマホ教室だと、個人個人の課題が解決できないですし、個別対応は設計が大変だなと感じています。まだまだ試行錯誤している最中で、学生からも難しかったという声がありました。スマートフォンは機種やバージョン、携帯会社によって使い方が異なる点や、シニアの方々の質問のレベルが高いという声もありました。今後は「~曜日~時から」というように決めて、学生5人を配置して、質問がある方に来てもらうという形にした方が、広報や運営面からも良いかなと考えています。
さぽーとほっと基金の助成金からは、会場費や広報費をいただいていますが、NPO法人シーズネット(wacco連携団体。高齢者の仲間づくりなどを行う)にも、活動を支えてもらっています。8月17日の北海道新聞に、8月のYouTube教室について掲載されましたが、参加の申し込み受付はシーズネットに取りまとめてもらいっています。イベントへの参加もシーズネットの会員の方が多く、一般の方へはあまり広報できていません。
 いろんなことやってみたい
いろんなことやってみたい
― 今後の活動についてお聞かせください
waccoの会員は現在約120人います。みんな札幌市内の大学生ですが、半数以上が北海道大学の学生です。タイミングが合えば来てくれるという感じなので、高齢者からの依頼を受けることも大事ですが、学生のやる気が出るようにwaccoって面白い!とアピールすることも大事だなと思います。
スマホ教室はやる意味があると感じています。スマホを使うことができるだけで、毎日の楽しさが変わるのだと実感しました。これまでの生活支援サービスとしては、こういったサポートは行ってませんでしたが、これからは頑張っていきたいです。

インタビューを振り返って
お話を聞く前は、シニアの方々のお手伝いをするというイメージだったのですが、お話を聞いてからは学生にとっても気づきを与えてくれる活動だと感じました。ただ一方的に何かをしてあげるのではなく、その中で学生がシニアの方々はこういうものを求めているのか、ここが知りたいと思っているのか、というような気づきから、次の活動へと繋がっているのだなと思いました。また、お店のポイントカードなど日常で使うものや連絡手段として使っているアプリもスマートフォンしか対応していないものが多くなっています。キャッシュレス決済しか対応していないというお店も出てきており、高齢者の方にとってはハードルの高いものとなってきています。waccoさんが行うスマホ教室は、高齢者のより豊かな生活にも繋がると感じました(秋本)
インタビュアー
秋本伊織(あきもといおり)
北海道NPOサポートセンターインターン
北海学園大学3年
※インタビューは、2023年8月22日wacco事務所にて行いました。

[インタビュー]対話の中から感じてもらう~サステナビリティ・ダイアログ 牧原さん・清山さん
![[インタビュー]対話の中から感じてもらう~サステナビリティ・ダイアログ 牧原さん・清水さん](http://cdn.goope.jp/164450/230622144120-6493df007f0d0.jpg)
一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ
宇宙船地球号ミッション! 2022秋~SDGs・環境教育ワークショップ
(令和4年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 子どもの健全育成分野)
一般社団法人サステナビリティ・ダイアログは、社会が無理なく続いていくためのサステナビリティ(持続可能性)、必要な知識や智恵をたくさんの人と共有・創造・実践できる場をつくるためのダイアログ(対話)を重視し、持続可能な社会を実現するための知識・認識に関する教育の研修やワークショップなど実施しています。
今回は、代表の牧原百合江(まきはらゆりえ)さん、このプロジェクトの事務局の清山美咲(きよやまみさ)さんに話しを伺いました。
※右写真:宇宙船地球号ミッション、プログラムの様子
 『持続可能』ってなに?
『持続可能』ってなに?
― まず、サステナビリティ・ダイアログの活動について教えてください
サステナビリティ(持続可能性)を高めるためのダイアログ(対話)の実践を呼びかけながら、大きく3つの活動を行っています。
①地球を1つのシステムとして包括的に理解する知識の普及
②自然/社会環境問題に協働で取り組むために本質的な人間関係を構築する仕組みづくりの活性化
③違いを越えて人と人とがつながるための参加型リーダーシップの普及
に取り組んでいます。
特に『持続可能な社会づくり』における「『持続可能』ってなに?」ということについて、フレームワークを使った基礎教育を行っています。そして、大人も子どもも一緒に学んで考えて、対話の練習をしていくということも大事にしています。
 宇宙船地球号ミッション
宇宙船地球号ミッション
― 今回の助成事業の内容や経緯について教えてください
主に小学生を対象として、「宇宙船地球号ミッション」と題したオンラインによるワークショップを実施しました。1回目は2時間30分、2回目は3時間、2週に渡って、札幌の子どもたちが、福岡や沖縄の子どもたちと交流しました。他の地域の子どもたちと話すことで、自分が住むまちの成り立ちを、対話から感じてもらうのが狙いです。“教える”という形ではなく、対話の中から感じてもらうための授業となっています。
「宇宙船地球号ミッション!」は、2021年3月に、SD(持続可能な発展/開発)のために必要な知識やスキルを、子どもも大人もそれぞれ一人の”地球人”としてつながって学ぼうという目的でスタートしました。コロナ禍でたくさんの人数は集まれないけれど、全国各地で同じテーマに取り組む子どもたちや、オンラインの先で話を聴いて、グラフィックレコーディングをしてくれる仲間ともオンラインでつながって交流しながら、「みんなが幸せに暮らせるロケットを開発しよう!」というミッションに取り組みました。
当初は札幌だけでの実施でしたが、このプロジェクトへの共感の輪が広がり、現在は北海道から沖縄まで全国各地でつながった対話の場が実現しています。開催地が広がったことで、子どもたち同士で、どこに住んでいるの?という会話から、相手の地域の環境や文化に驚いたり、関心を持ったりということがありました。子どもたちにとっては、些細な違いが新鮮なのだと、あらためて感じます。
このプログラムでは、最後にそれぞれの研究所が考えたロケットをお互いに発表しながら、「自分の研究に役立てたいと思ったポイント」や「いいね」と思ったポイントを見つけていきます。同じ事を他の地域の人もやっている、1つの星でつながっているということを、実感してもらえたのではないかと思います。
工夫した点としては、子どもたちが学びたいように学べる場を支えるために、子ども研究員の見守り役である「ミッションアシスタント」がいるということです。そのために事前の準備や研修など時間をかけて当日を迎えています。当日どのようなサポートがあったら過ごしやすいか、まずは自分自身が当日の流れを体験しながら、会場に必要なものを準備したり、過去にミッションアシスタントをしたことがある人の知恵から学ぶ時間を過ごしました。
ミッションアシスタントは、子育て支援団体に所属している方から中高生まで地域によって様々です。私たちが対話の実践として呼びかけている「参加型リーダーシップ研修」をきっかけに参画される方が多いです。対話の見える化をするグラフィックレコーディングの技術を学んでいる方の参加も多いですし、過去の参加者だった子どもが見守る側(ミッションアシスタント)になっていて、循環が始まっています。
準備段階においては、どのように見守るのか、という点での質問が多かったです。このプロジェクトでは、子どものありのままの声を“聴く”ということを大切にしています。事前の研修や準備段階で、「子どもたちに対して指示しなくても大丈夫か」という不安を抱いていた方もいましたが、終わってみると、これで良かったんだ、という自信、確信が持てたようで、子どもとの関わりについて学びがあったようでした。
 地域における『器』をつくる
地域における『器』をつくる
― 今後の活動や課題についてお聞かせください
「宇宙船地球号ミッション」に参加したいという子どもたちからの声が増えてきましたが、それを支える『器』、地域における『器』をつくることが課題だと思います。求められたらいつでもできるようにするためのチーム作りですね。このワークショップは、大人1人で子ども50人を見るわけにはいきません。見守る人が増えないとできないミッションです。開催できる地域が限られているのが現状ですが、札幌のNPOとの提携も始まっていて、徐々に広がりを見せています。参加する子どもが増えて欲しいのと同時に、見守る大人も増えて欲しいです。
私たちの活動への関わり方は3つです。子どもは「宇宙船地球号ミッション」に参加する。大人の方は研修への参加や、記録するなど役割をもって関わることができます。
また「マンスリークルー」という形で、継続してご寄付いただける方を募集しています。どの地域でも、ワークブックや研修用動画を作成しているので、運営のためのご支援をお願いしています。
子どもたちが、自分で考え、他の地域の子どもたちとつながろうとしている姿を実際に見ると、きっと驚かれると思います。その感動をぜひ体感していただきたいです。ホームページには活動の様子が分かる動画も公開していますので、興味を持たれた方のご連絡をお待ちしてます!

インタビューを振り返って
持続可能な社会という大きな目標を目指して、地球を1つの船に見立てたプログラムを用いて、大人も子どもも共に学ぶ活動をされていました。今回の助成事業では、日本各地を結ぶことで、子どもたちがお互いの地域のことに関心を持ったり、距離を感じつつも1つの星に住んでいるという感覚を抱いているようでした。16箇所を結んでのオンラインプログラムの綿密な準備作業のお話しも、とても印象深いものでした。事業名が示唆するように、地域を選ばない活動ですが、各地域で子どもたちとともに活動する方が必要です。ご関心の方はぜひお問合せいただければと思います。(高山)
インタビュアー
高山大祐(たかやまだいすけ)
北海道NPOファンド
※インタビューは、2023年3月30日オンラインにて行いました。

[インタビュー]多様性の受容を社会に訴えることで社会の豊かさへつなげたい~さっぽろレインボープライド実行委員会 長谷川さん
![[インタビュー]多様性の受容を社会に訴えることで社会の豊かさへつなげたい~さっぽろレインボープライド実行委員会 長谷川さん](http://cdn.goope.jp/164450/230629103226-649cdf2a347c8.jpg)
さっぽろレインボープライド実行委員会
LGBTパレード開催を通じた、性的マイノリティ当事者の抱える諸問題(存在の否定・孤立・社会制度上の不平等)の解消に関する事業
(令和4年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 まちづくりの推進分野)
さっぽろレインボープライド実行委員会は、様々な立場に生きる市民が自分らしく生存できる社会づくりを求め、パレードを通じて、広く社会全体へ訴えかけています。そして、身近にLGBTQが存在することを前提とする社会制度の構築と、多様性を認め合い個性を尊重する豊かな社会の実現を目指しています。
今回は、実行委員の長谷川諒(はせがわりょう)さんにお話を伺いました。
※右写真:2022年のパレードの様子
 もっと社会全体を巻き込んだ総合性のある活動に
もっと社会全体を巻き込んだ総合性のある活動に
― 今回の助成事業について教えて下さい
LGBTQセクシャルマイノリティ当事者の可視化であったり、権利の主張であったり、当事者間では情報交換や交流を目的としています。昨年9月に、札幌市内中心部の歩行者天国を使って、著名人をゲストに呼び、企業や団体にインタビューをしたり、パフォーマンスであったり、公開メイクショーといったステージイベントやブース出展を行いました。そして、メインプログラムとして、装飾した車の後ろを30~40分かけてパレードを行いました。
― このイベントの経過についてお聞かせください
札幌のLGBTQパレードは、実は東京の次に古く、日本で2番目の1996年に始まりました。そのころはまだ、LGBTQに対して理解が低く、あるいはヘイトを向けられるような対象という時代だったと思いますが、権利の主張と存在の可視化というのを強く意識したイベントでした。そこから、少しずつ認知されてくるようになったかなと思います。「LGBTQ」という言葉自体をまったく聞いたことないという方は、今ではほとんど居ないんじゃないかな。
一方で、権利という法で守られた存在ではありません。もっと企業や社会全体を巻き込んだ、総合性のある活動にしたいです。当初は1つのセクシャリティの方しか参加していませんでしたが、今では様々なセクシャリティの方が参加・運営に携わっています。
― コロナ禍での活動で工夫していることを教えてください
前年(2021年)、前々年(2020年)に関してかなり縮小して実施しました。メインイベント以外ではオンラインのイベントや配信を取り入れてみました。北海道という土地柄、遠方の方や、全国各地の方に参加していただけることもあり、オンライン上でメインのパレードイベントを周知して、二次的な集客に繋がるといったようなことも、オンライン開催でプラスに働いた感じました。運営側としても、比較的お金も掛けずにできることも、オンライン開催の良いところかと思います。

「この街で私らしく生きていく」

テレビ塔も虹色にライトアップ
 セクシャリティの垣根を超えた交流の場に
セクシャリティの垣根を超えた交流の場に
― 新たな気づきや今後の課題を教えてください
私自身が初めてパレードに参加したのは10年以上前なのですが、その時から比べると、社会の雰囲気であったり、大きな企業が関わってくれるようになったというところが、大きく変わってきています。
イベントだけを、ただただ大きくして開催する、というのは意外と出来てしまうんだな、ということを昨年感じました。同じセクシャリティ同士の友達はいるし、同じセクシャリティ間の交流はよくありますが、抱えている問題はセクシャリティによって違うこともあります。もっとセクシャリティの垣根を超えた交流の場が増えるといいなと思います。運営面では、実行委員側の人員の確保や、仕事の割り振りは、毎年四苦八苦しているところです。活動に共感して協力してくれる人をどれだけ集められるかというところが、課題だと思っています。

インタビューを振り返って
社会のLGBTQに対する認識が変わってきてはいるものの、当事者の中には、いまだに孤独を感じている方が多いという。LGBTQに関わらず、人々がもっと生きやすい、ありのままの自分を出せる社会になることを願う今日このごろです。(斎藤)
インタビュアー
齊藤博美(さいとうひろみ)
北海道NPOサポートセンター
※インタビューは、2023年3月28日にオンラインにて行いました。