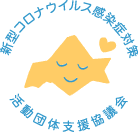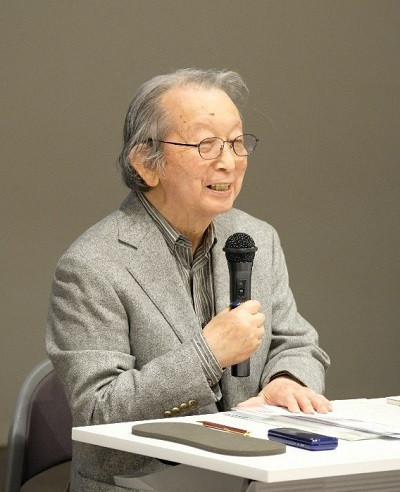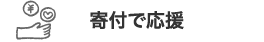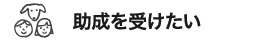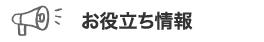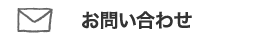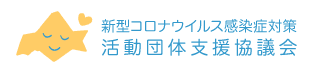団体からのお知らせ・インタビュー
【4/1‐4/17受付】令和6年度地域課題解決のためのネットワーク構築事業のご案内[札幌市]

少子高齢化や担い手不足などの社会情勢の変化に伴い、地域の抱える課題は複雑・多様化しています。このような社会情勢においても、札幌市の持続的な発展を支えていくためには、多様な活動主体の連携・協力を通じたネットワークを構築し、市民まちづくり活動を推進していくことが必要と考えます。
本事業は「ネットワーク事業」と「地域連携促進事業」の2つのメニューから、地域課題の解決に取り組む活動や異なる活動団体の連携構築を支援し、市民まちづくり活動の推進を目指しています。
 ネットワーク事業
ネットワーク事業
NPOが町内会や事業者などの異なる活動団体と連携・協働し、継続的に地域の課題解決及び活性化等に取り組み、活動の持続によって地域力の底上げを図る新たな事業を募集します。
これまでは単年度のみの支援でしたが、地域課題に取り組む団体を継続的に支援するため、3か年度を上限に継続して申請できるよう制度を一部変更しました(継続する場合にも各年度の審査会で採択される必要があります)。
●各年度における補助金上限額は以下のとおりです。
【1年目】 200万円又は補助対象経費の90%のいずれか低い方
【2年目】 100万円又は補助対象経費の90%のいずれか低い方
【3年目】 50万円又は補助対象経費の90%のいずれか低い方
●募集期間:令和6年4月1日~4月17日まで(15時必着)
 地域連携促進事業
地域連携促進事業
まちづくりのスキル・ノウハウ・アイデアを有しており、当該スキル等を活用した取組を新たに地域で始めたいと考えているNPOを募集します。
審査に通過した各NPOの概要やスキルをまとめたPR冊子を作成して、町内会をはじめとする地域に配布し、活動を希望する地域を募集します。地域から活動の申込があった場合にその地域へ対象NPOを派遣して、地域とともに活動を行っていただきます。地域で行う活動費について金銭的な支援をするとともに、スムーズに地域での活動が行えるよう支援します。
●補助額:1活動あたり 上限5万円
●募集期間:令和6年4月1日~4月17日まで(15時必着)
【お問い合せ】
札幌市市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階
電話番号:011-211-2964
ファクス番号:011-218-5156
【3/13締切】令和6年度 さぽーとほっと基金・前期助成事業等 締切間近!

さぽーとほっと基金・令和6年度の前期助成事業 募集中!
さぽーとほっと基金は、札幌市が募集し、町内会・ボランティア団体・NPOなどが行うまちづくり活動に助成することで、札幌のまちづくり活動を支える制度です。
2月14日より、令和6年度前期の事業募集が開始となりました。
【募集期間】
令和6年2月14日(水)〜令和6年3月13日(水)15時まで(期間内必着)
※「新型コロナウイルス感染症対策市民活動基金」としての募集はありません。
さぽーとほっと基金の制度が変わりました。詳しくは募集要項をご確認ください。
・助成額の上限の廃止
・同一事業は3回まで
・一部事業の助成率の増率
・事業期間の短縮
・プレゼンテーション審査の時間拡大
・被災者支援活動基金について
【お問い合わせ】
札幌市市民文化局 市民自治推進室 市民活動促進担当課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 電話:011-211-2964
FAX:011-218-5156 E-mail shimin-support@city.sapporo.jp
[3/4@札幌エルプラザ]支援協議会事業報告会&さぽーとほっと基金など助成金・補助金に関する説明会
![[3/4@札幌エルプラザ]支援協議会事業報告会&さぽーとほっと基金説明会](http://cdn.goope.jp/164450/240209134800-65c5ae808a744.gif)
新型コロナウイルス感染症対策活動団体支援協議会は、2023年度さぽーとほっと基金採択団体および応募団体を対象とした、相談窓口、伴走支援事業のため、このたび報告会を行なうこととしました。今回の伴走支援では10団体にお申し込みいただき、団体の皆様へヒアリングを行い、団体の皆様とともに課題の整理・見直しを行って必要な支援や支援の方向性を検討し、訪問やオンラインにより面談を重ねて、団体の課題解決や目指す姿の実現を応援しました。報告会では支援の概要や最近の助成金の動向などについてお伝えします。
さぽーとほっと基金令和6年度助成における変更点、地域課題解決のためのネットワーク構築事業に係る補助金の説明も併せて行います。
ぜひご参加ください。

●日時/2024年3月4日13:30~16:10
●場所/札幌エルプラザ2F 会議室1・2
●参加無料・定員40名(申込先着順)
●参加者募集期間/2月13日(火)から2月29日(木)まで ※お申し込みは先着順として、定員になり次第、締め切ります。
●お申し込み/メール(kyougikai@hnposc.net)または下記リンクよりお申し込みください。
 プログラム
プログラム
第1部 新型コロナウイルス感染症対策活動団体支援協議会報告
「NPO活動におけるこれからの資金調達、「共感」の集め方」
・伴走支援等の非資金的支援付きなど最近の助成金・補助金の動向・テーマ
・共感を集め、事業を成功・発展・継続させるために必要なこと、課題、成功事例
第2部 さぽーとほっと基金 令和6年度助成における変更点について
第3部 地域課題解決のためのネットワーク構築事業に係る補助金について
【お問い合せ・申込先】
新型コロナウイルス感染症対策活動団体支援協議会 事務局
(北海道NPOサポートセンター内 担当:高山・中西)
電話:011-200-0973(平日10時~18時)
FAX:011-200-0974
メール:kyougikai@hnposc.net
[インタビュー]座長・鈴木喜三夫とともに~座・れら 戸塚さん
![[インタビュー]座長・鈴木喜三夫とともに~座・れら 戸塚直人さん](http://cdn.goope.jp/164450/240119115502-65a9e48627a99.jpg)
座・れら
劇作家・山田太一作品を通じて考える超高齢社会と生きることと死ぬこと
(令和5年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 長内芸術振興基金助成事業)
座・れらは、札幌を拠点に新劇の伝統に立脚し、人の気持ちに寄り添い、人の心に響く良質な演劇作品を多くの人と共有しようと活動しているアマチュア劇団です。本業を持ちながら旗揚げ公演以来18回の本公演や若手の育成公演などをおこなっています。
今回は旗揚げメンバーで演出家の戸塚直人(とつかなおひと)さんにお話を伺いました。
※右写真:戸塚さん(座・れら事務所にて)
 持続可能な演劇を目指す
持続可能な演劇を目指す
― まず、団体の活動などについてお伺いします
職業演出家の鈴木喜三夫を中心に、2009年3月に4名で発足した劇団です。現在の団員は私のように仕事を持ちながら10名が参加しています。主な活動は演劇公演ですが、演劇誌「風」の発行を通じて、演劇を行うことはどういうことかの考察なども行っています。座名の「れら」はアイヌ語で「風」という意味です。観客を含めた参加者が納得し、高い満足感を得られるような持続可能な演劇を目指しています。
1931年生まれの92歳で道内最高齢の演出家の鈴木喜三夫は、民主的に舞台つくりを進め、「俳優がいかに舞台で生きられるかを手助けするのが演出家の仕事だ」と言います。そのため稽古場は常に和やかな雰囲気です。
 生き死にを共に考える機会を、芝居で
生き死にを共に考える機会を、芝居で
― 今回のさぽーとほっと基金の助成事業についてお伺いします
超高齢社会を我が事として捉え、いかに生きて、いかに死ぬかということを、山田太一作品を通じて考えるため企画しました。8月にはプレ企画として鈴木喜三夫が演出の山田作品の紹介と山田太一作『林の中のナポリ』の試演会をおこないました。10月には文化芸術交流センターで同様の企画を実施しました。12月1~3日には座・れら第19回公演『林の中のナポリ』を計5公演おこないます。
『林の中のナポリ』は、客足が途絶えた高原のペンション「林の中のナポリ」にたどり着いた高齢女性が主人公です。高齢女性の生き様を軸に周囲の人々の思いが浮き彫りになっていく山田太一ならではの作品です。とても良い芝居に仕上がっていますので、ご期待ください!

演出家鈴木喜三夫と劇作家山田太一を語る会と『林の中のナポリ』公開稽古(10月28日)の様子

座・れら第19回公演『林の中のナポリ』(本公演)より
 気づきを共有できる芝居を多くの人に知ってもらいたい
気づきを共有できる芝居を多くの人に知ってもらいたい
― 今年度は支援協議会が伴走支援を行っていますが、特に期待していることをお聞かせください
運営の基本は入場料収入ですが、赤字のときは団員が補っています。良質な作品つくりにはどうしても経費がかかり、多くの公演は赤字で、運営はうまくいっているとは言えません。観客動員のために外部に発信していく効果的な方法があれば教えてほしいです。助成金の申請についてもアシストしていただけると助かります。
― 今後の活動について教えて下さい
コロナ下では、演劇など文化芸術は生活に必須ではないと思われたようで、多くの公演等が中止に追いやられました。ほんとうはなくてはならなかったと思います。人は食べ物だけで生きられるわけではありません。芝居づくりは気づきの連続です。私たちが気づいたことを、できれば皆さんと共有したいと願っています。ホームページやSNSも充実させたいと思います。

インタビューを振り返って
私にとって劇団のイメージは、大学に結びついていて、そのためか、活動は難しい理論に支えられているのだろうなと思っていましたが、観る側によって気づくところも異なる、気づきの機会としての演劇のことを、分かりやすくお話ししていただきました。コロナ感染症の時期に、当たり前のことが当たり前でなくなったときに、何が大事であったのかに気づかされることもありました。そのような気づきの機会をつくる活動がこれからますます必要になると感じました。(高山)
インタビュアー
高山大祐(たかやまだいすけ)
北海道NPOファンド
※インタビューは、2023年9月23日に座・れら事務所にて行いました。

[インタビュー]心のメンテナンスを自分でできるように~ホリスティックケア協会 森さん
![[インタビュー]心のメンテナンスを自分でできるように~ホリスティックケア協会 森さん](http://cdn.goope.jp/164450/231129152230-6566d8a65d187.png)
一般社団法人ホリスティックケア協会
心のケアを自分で行い楽観脳を創る「キラリノート」を社会と学校に普及させ、子供達にメンタルの整え方を教授し心の成長と進化する力を育む事業
(令和5年度札幌市市民まちづくり活動促進助成金 まちづくりの推進分野)
一般社団法人ホリスティックケア協会は、協会オリジナルの『キラリノート』を使い、メンタルに特化した自己啓発講座をオンラインにて開催しています。
今回は代表理事の森由佳子(もりゆかこ)さんにお伺いしました。
※右写真:森由佳子さん
 心の不調を自分で整えられるノートを開発
心の不調を自分で整えられるノートを開発
― まず、団体の活動などについてお伺いします
2015年に団体を設立し、誰でも受講できるメンタルに特化した自己啓発講座を開催しています。オリジナルの『キラリノート』に書くことで、自分の心を整えたり、不安な感情を解消したり、自分がやりたいことを成し遂げるためにはどうすれば良いのか、といったことが自分で整えられるようになります。
オンライン講座は、『キラリノート』に感情を書き、自分自身と向き合っていくものですが、動画や呼吸法、ワークショップなども取り入れています。さらに、認定講師制度を設けています。私たちと共に講師として活躍していただく方を養成して、この講座自体を広めていきたいと思っています。
― 『キラリノート』について詳しく教えてください
私がセラピストの仕事を通じて苦しんでる方にたくさん出会い、どうにかできないかと考え、自分自身も苦しい思いをしたことがありました。ちょうどその頃、認知行動療法に出会い、私自身が一瞬で明るくなったことを実感しました。自分の考えの‟癖“のようなものを変化させ、ネガティブ脳をポジティブ脳に変えるようなイメージです。
書籍やセミナーでの勉強はもちろんですが、大学の心理学科に通い学び直し、心理系の資格も取得しました。脳科学者の中野信子先生や、精神科医の樺沢紫苑先生らは、私がとても好きで影響を受けた方たちです。この方々から学んできたものを実際に試し、効果がとても高いものを集め、さらに自分の気持ちを解消できたものを組み合わせることで、このノートを作りました。制作にあたっては多くの方にご協力いただき、実際に試しながら何回も作り直し、完成するまで2年ほどかかりました。
― さぽーとほっと基金の助成事業についてお伺いします
『キラリノート』を社会や学校に普及させることを目的に申請しました。当初、子ども向けに作成したいと思っていましたが、私が実際に体験しながら作ったので、最初に社会人用ができました。次は10歳から中学3年生までの子ども用、そして高校生から大学生までの学生用というものを作りたいと考えていて、これから学校に普及させていきたいです。
 多くの人が効果を実感。受講後も手厚くサポート
多くの人が効果を実感。受講後も手厚くサポート
― 講座の概要を教えてください
講座には5つのカテゴリーがあります。最初は約30分の動画を見ながら、自分で『キラリノート』を書いていくので、1カテゴリーにつき30分から1時間ほどかかります。その後、グループになり90分のワークショップを行います。これをZoomで約3か月間かけて行っています。
また、講座を受けたら終わりではなく、ここからが本番だと思っています。講座は心のメンテナンスを日常的に自分でできることを目的としており、受講だけでは独り立ちするには時間がかかる上、難しいところもありますので、きめ細かいサポート体制を作りました。
― 講座の反応はいかがですか
オンラインということもあり全国から延べ100名以上が受講しています。受講者には向上心のある方が多いですが、会社の人間関係や、家族との関係、親から暴力を受けていたという方など、様々な悩みを抱えている方がいらっしゃいます。
実際に受講し、効果を実感された方からは、「とても良いものだね」という感想や、講師になりたいという声をいただきました。ご自身の気持ちが変化してくることを実感できるので、やってるうちにどんどん楽しくなってくるようです。
また、コロナ禍を機に自分の得意分野をオンライン事業で起業したいが、どうしたら良いかわからないといった方が多くいらっしゃいますので、その中でも特に女性起業家の皆さんに受講していただきたいと思っています。しかしながら、インターネットの情報が多くなった昨今、集客がとても難しくなりました。
― どのように活動に関わることができますか
ぜひ、認定講師を目指したい方に関わっていただきたいと思っています。コンテンツも揃っていますので講師になることは難しくありませんし、何を学んで何を教えなければいけないということも一切ないので、関心や気力さえあればできると思っています。いずれ子ども向けの『キラリノート』を作りたいと考えていますので、協力してくださる方がいると嬉しいです。怒りの感情などの苦しい思いを、自分で簡単に解放できるとすごく楽になります。一緒に広めていただける方に協力してもらいたいと思います。
 唯一無二のメソッド
唯一無二のメソッド
― 森さんが考える強みと弱みはなんでしょうか
やはり『キラリノート』が一番の強みです。認定講師はコロナ禍でやめざるを得ない方もいらっしゃいましたが、講師が増えて助け合えるような関係になると、さらに強みが増すと思っています。現在は、ほぼ1人で活動をしているので、意思決定は早いというメリットがありますが、これから雑務が多くなってくると大変だなと思っています。
コロナ禍については、結果的に追い風になったのではないかと思っています。コロナの行動制限緩和で再びリアルで会うこともできるようになりました。ただ、情報過多になり、活動当初の8年前には居なかった同業者が、今では多くなったと感じるようにもなりました。『キラリノート』はオリジナルツールですし、似ていたとしても、完全に同じものは無いと思っています。ただ、キラリノート講座の知名度は、告知の仕方が悪いのか、まだまだ浸透していないというのが実態です。
― 今年度は支援協議会が伴走支援を行っていますが、特に期待していることをお聞かせください
伴走支援を申し込んだ動機としては、SNSの活用を含め,集客がうまくいっていないことが大きな理由です。私がSNSを使って団体の発信を行っていますが、SNSの種類によって雰囲気も違いますし、飛び交ってる言葉も違いますから、どう表現したら良いのかわからず苦手です。とは言っても、経営者としては頑張らなければならないところなので、SNSを使った集客に関する部分については特にお力を頂きたいと思っています。
― 今後の展開について教えて下さい
学校の先生方に講座を受けてもらいたいと思っています。はじめに社会人用の講座を受けて効果を実感してもらってから、次に子ども用の講座を先生方に体験していただくことが理想的だと思っています。
受講した方々から「子ども用を早く作ってほしい」と言われたこともありますが、社会人用と子ども用とでは、本質的なものは変わりませんので、早く子ども用を作りたいと思っています。

インタビューを振り返って
ホリスティックケア協会さんは、『キラリノート』に書いていくことで、自分を見つめ直して、自己肯定感を高めていくことを目指されています。自由な発想を重視するNPO活動においても、コンプライアンス、ガバナンスの要求は以前よりも高まっており、職場の人間関係や活動現場や情報発信において神経を使う場面が増え、悩みを抱えている方も多いのではないかと思います。こうした活動のニーズは、今後も増えていくと思われますので、これからの展開に期待したいです。(高山)
インタビュアー
高山大祐(たかやまだいすけ)
北海道NPOファンド
※インタビューは、2023年9月6日に北海道NPOサポートセンター事務所にて行いました。